視覚的でわかりやすいトレンド系テクニカル指標
一目均衡表の使い方が分からない

どこで抵抗されるか。どこで支持されるか。短期、中期的にどのようなトレンドなのかが一目で分かる。
一目均衡表は視覚的に分かりやすい!
・どこで抵抗線されるか
・どのようなトレンドか
パット見るだけで大体が分かります。
そんな魔法のツール一目均衡表を使っているトレーダーは多いのに、
何故か勝てる人は少ない。
この一因として適切に使えていないトレーダーが多い
というのが現状です。
本ページでは、
線一本一本に意味がある一目均衡表の意味を解説しつつ、
どのように使えばいいかを紹介していきます。
投資は、
テクニカル分析だけ学べば100%勝てるという甘い世界
ではありません。
しかし、私たちのトレードの判断基準としては十分に有効であるため、
学んでいて損はありません。
一目均衡表をマスターして、
負けにくいトレーダーになりましょう!
一目均衡表の見方
一目均衡表の見方について実際にDMM FXのチャートの
初期設定の色で説明します。
欲しい機能が盛りだくさんな五つの線

基準線(中期目線)
基準線は当日を含む過去26日間の最高値と最安値の平均値を示します。
例として26日の間で、
最高値:105円
最安値:100円
だった場合は基準線は102.5円になります。
26日間の平均であるため中期的なトレンドを見る場合に使用します。
上向きだった場合は上昇傾向、下向きだった場合は下降傾向であることが分かります。
転換線
基準線は当日を含む過去9日間の最高値と最安値の平均値を示します。
そのため、基準線とは違い転換線は短期的なトレンドを見る場合に使用します。
先行スパン1、先行スパン2
・先行スパン1は基準線と転換線の平均値を当日を含めて26日先行させたもの
・先行スパン2は当日を含めた52日間の最高値と最安値を26日先行させたもの
そして、
先行スパン1と先行スパン2の間のことを雲といいます。
雲は
上昇トレンドの時:サポートライン(下値支持線。それ以上は下落しにくい)
下降トレンドの時:レジスタンスライン(上値抵抗線。それ以上は上昇しにくい)
として働きます。
サポートやレジスタンスは雲の厚さにより影響力が変わり、
厚いほどより強いものになります。
遅行スパン
遅行スパンは、
当日の終値を当日を含めて26日前にスライドさせたものです。
・遅行スパンとチャートの関係
・遅行スパンと雲の関係
から現在のトレンドを把握することができます。
上昇トレンドの時は、
雲、チャートの上を遅行スパンは推移しています。
下降トレンドの時は、
雲、チャートの下を遅行スパンは推移しています。
一目均衡表の使い方
基準線と転換線

①転換線が基準線を下から上に突き抜けた
⇒買いエントリー。売りポジションは手じまい。
②転換線が基準線を上から下に突き抜けた
⇒売りエントリー。買いポジションは手じまい。
上のPOINTをもとに上図について考えてみると、
上図において遅行スパンはチャートと雲の下を推移しています。
そのため、現在は下降トレンドといえます。
ゆえに下降トレンド中のため、
転換線が基準線を下から上に突き抜けたところでショートでエントリーします。
そして、転換線が基準線を上から下に突き抜けた点で利益確定をします。
雲について
再度掲載しますが、
雲は以下のように機能します。
上昇トレンドの時:サポートライン(下値支持線。それ以上は下落しにくい)
下降トレンドの時:レジスタンスライン(上値抵抗線。それ以上は上昇しにくい)
それでは実際のチャートで考えてみると、
といったように、下降トレンド時はレジスタンスとして考えることができます。
白〇で示している部分はレジスタンスとして機能するものと考えられますが、
雲も厚いので実際に抵抗されると予想できます。
一目均衡表の注意点
一目均衡表は沢山の機能を備えていて、
雲も視覚的に見やすいため多くのトレーダーに愛用されています。
しかし、もともとは株式のチャート分析のために考えられたものであるため、
株式ほどFXでは機能しないと言われています。
特に雲がサポート、レジスタンスとして機能しにくいと言われています。
そのため実際に使用する場合は、
・補助的に使用する
・他のオシレータなどと組み合わせて使用する
ことが推奨されます。
また株式用と作られたことから、
日足用で作られている!
スキャルピングなど短い時間足での使用は不向き!
一目均衡表について
都新聞の商況部長として活躍した細田悟一氏(ペンネーム:一目山人)によって考案され、
1936年に発表された。
外国人トレーダーからも「Ichimoku」として親しまれ、世界中で使用されています。
原著について詳しくは一目均衡表公式ホームページを参照してください。
テクニカル指標学習におすすめの本
テクニカル分析を勉強する際に、
どのような指標があるのかを知る必要があります。
何を使えばいいのか。
どのように使えばいいのか。
どういうときに使ってはダメなのか。
それらが簡単に学べる本を紹介させていだきます。
実戦相場で勝つ!FXチャート攻略ガイド
FXのチャート分析をいちから学びたい初心者にとっては、
まさにうってつけの一冊です。
『実戦相場で勝つ!FXチャート攻略ガイド』では、
ローソク足の基本や移動平均線・ボリンジャーバンドといった定番テクニカル指標の使い方が、
豊富な図解と実際の相場例を交えて丁寧に解説されています。
専門用語もしっかり補足があり、初めてでもスムーズに読み進められます。
また、エントリーとイグジットのタイミングや損切りラインの設定など、
実際のトレードで役立つノウハウが具体的に示されている点も魅力です。
はじめてFXに挑戦する方や、基礎を復習しながらステップアップしたい方に特におすすめできる、
実践的で分かりやすい入門書だと思います。
マーケットのテクニカル分析 ――トレード手法と売買指標の完全総合ガイド
価格が高すぎるのがネックな本書。
私は購入はせず、Kindle Unlimitedで数年前に読みました。
ローソク足の基本的な見方、代表的なチャートパターン、主要なテクニカル指標やサイクル理論など、
テクニカル分析に関わる内容を網羅的に扱っているのが本書の特徴です。
テクニカル分析の基礎を身につけたい初心者にとっては、
理論をじっくり学ぶ教材として最適です。
また、トレード歴が長い人にとっても、
改めて基本を押さえたり新しい見方を発見できることもあるでしょう。
テクニカル分析の「総合ガイドブック」として、
おすすめの一冊です。


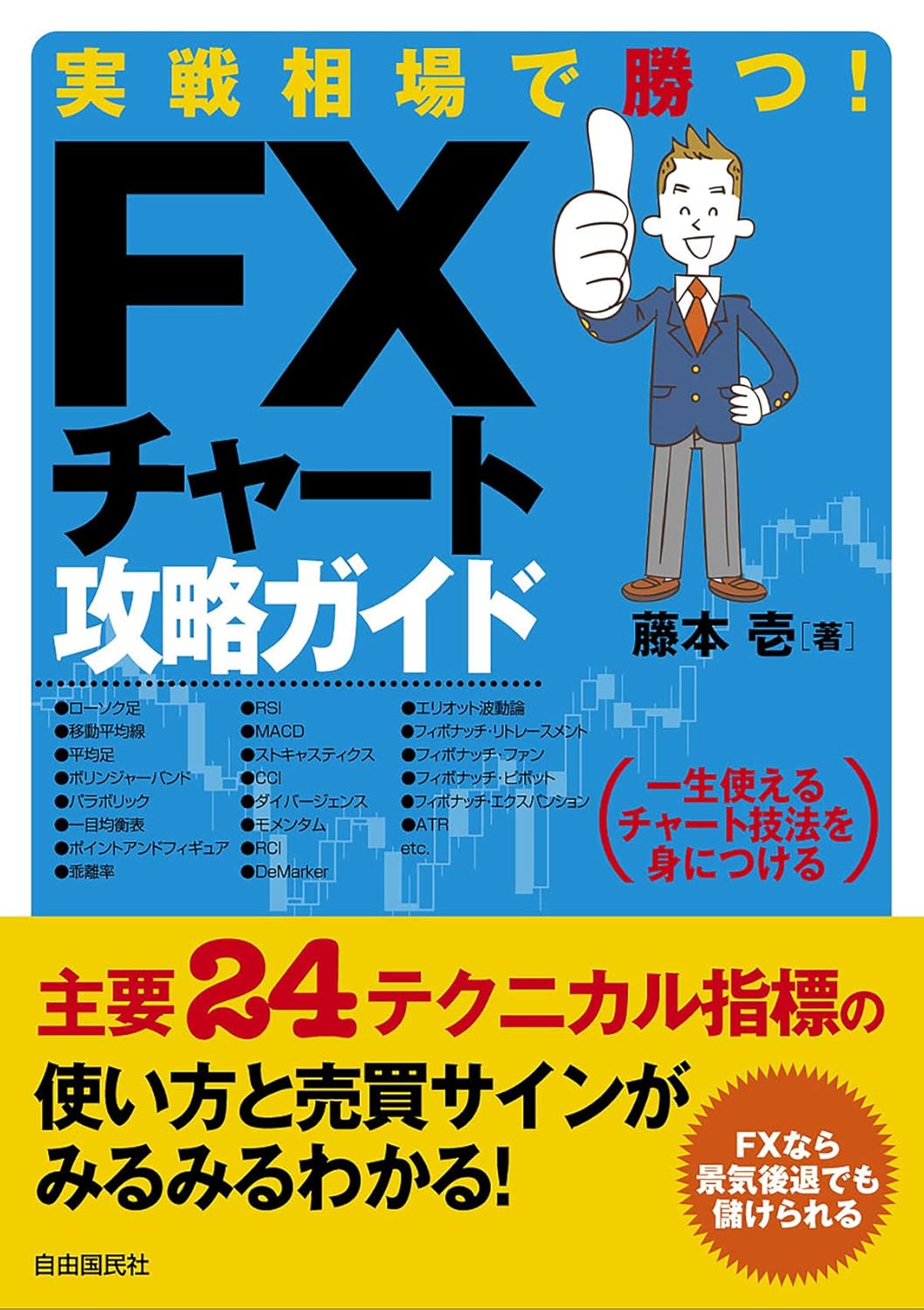
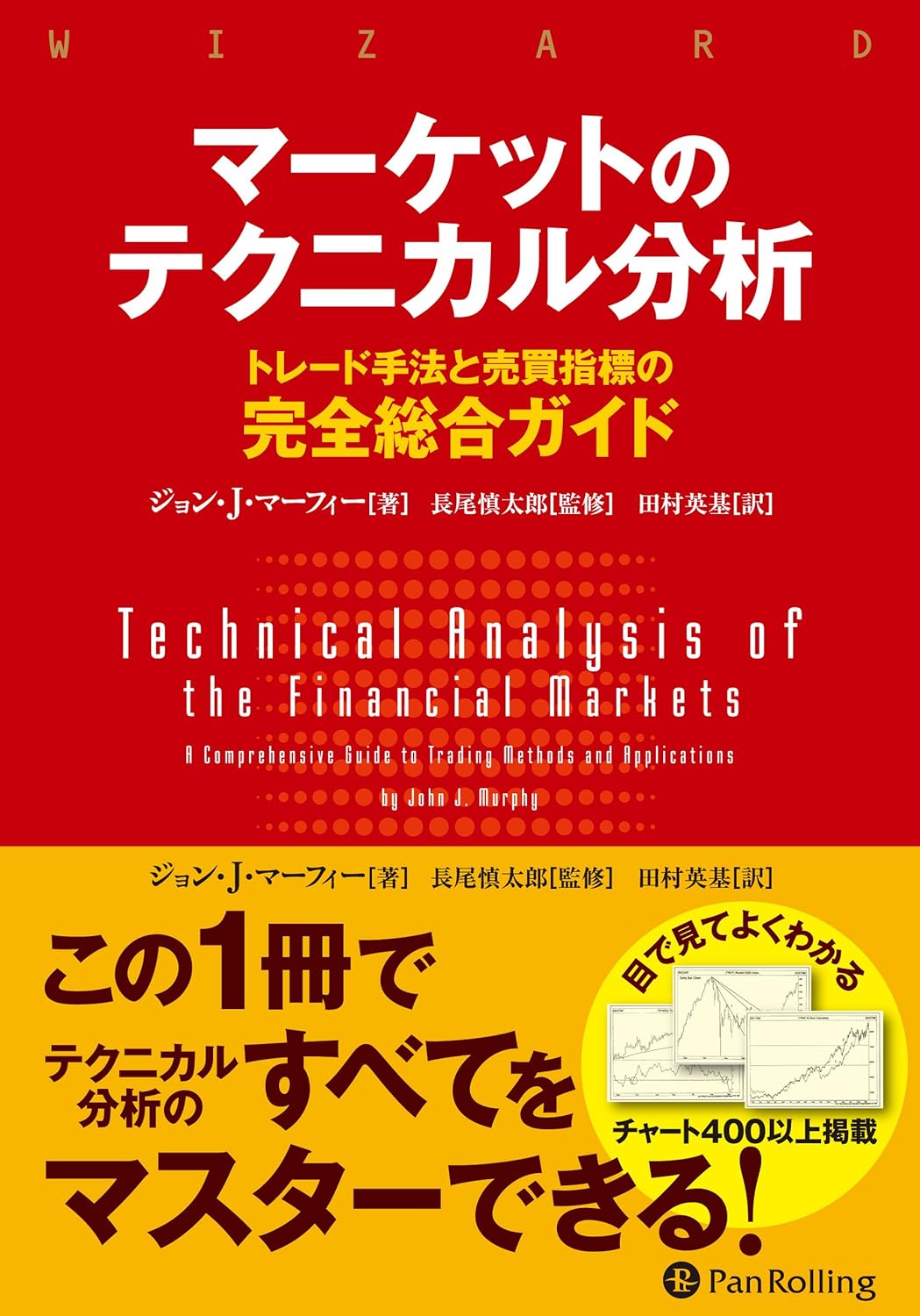
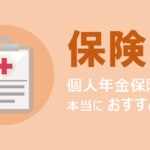


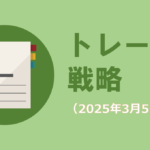
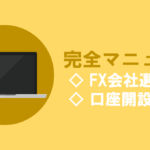
コメント